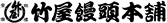竹屋でほのぼの旧暦くらし
なぜ5月5日に柏餅を食べるのか。
旧暦端午の節句(6/20)に昔からの風習の意味を知り、五感で季節を感じて頂く和の講座を催しました。
離れの坪庭で鶯が美しく鳴いて、まるでお出迎えしてくれているようでした。竹屋饅頭とお抹茶でおもてなしし、わらび餅や水無月風葛餅、アク抜きしない赤飯を笹で飾ってお出ししました♪
五感で旧暦くらしを体験し喜んでいただけてホッとしました。大雨警報の中、広島や三次から来てくださり感謝です。
講座の様子をレポートして下さっています。コチラ☆
東城本店 女将
ゴリョウエン(午良会)
東城では旧暦端午の節句(今年は6/20)をゴリョウエンと呼びます。
屋根の軒先に菖蒲とよもぎを束ねた菖蒲葺をさして邪気を祓い菖蒲湯に入る行事が今も残っており、菖蒲の葉先が魔除けの剣になるとか菖蒲とよもぎの強い臭いが邪気除けになるとかいわれています。
神様やご先祖様にもお供えするので菖蒲葺を50束娘と一緒に作りました。
昔は菖蒲やよもぎ、薬草を玉にして軒先に吊したとか。くす玉(薬玉)のルーツは邪気除けなのです。
東城本店 女将
父の日&母の日
娘達がお正月以来の帰省です。父の日のプレゼントは皆で作った採れたてじゃがいものコロッケ♪母の日と合わせてお祝いしました。
もう~パパの嬉しそうな事!
東城本店 女将
「祝い七つ菓子」
 昔から「祝い七つ菓子」といって、おめでたい時に身近にあるお菓子七種を盛ってお祝いする風習もあるそうです。
昔から「祝い七つ菓子」といって、おめでたい時に身近にあるお菓子七種を盛ってお祝いする風習もあるそうです。
「七」の数は、吉祥を意味するおめでたい数字だとか。竹屋の製品が只今六種類。七つ菓子になるよう新製品開発に取り組んでいます。
東城本店 女将
六月一六日は「和菓子の日」
「和菓子の日」があることをご存じでしょうか?
六月一六日に十六個の菓子や餅を神前に供えてから食べ疫病除けと健康招福を願う「嘉祥の祝」が始まりとされています。
江戸時代までは盛んにこの儀式が行われていたそうです。甘い物が貴重だった頃、嘉祥菓子を食べて本格的な暑さの夏を乗り切るようにしたんですね。
今日はご家族で招福を願い和菓子を召し上がりませんか?
東城本店 女将
クリーン作戦
 例年通り東城町中一斉に道路沿いの草取りや溝の清掃がありました。竹屋組もカメを利用した高圧洗浄機をトラックに括り付け出動致しました。
例年通り東城町中一斉に道路沿いの草取りや溝の清掃がありました。竹屋組もカメを利用した高圧洗浄機をトラックに括り付け出動致しました。
有る物を工夫して役立てる事。これも竹屋の家訓の一つです。
東城本店 谷
柏餅(いばら餅)
梅雨入り後の田植えを終えた美しい田園風景です。
6月20日の旧暦端午の節句を前にサルトリイバラの葉を見つけたので柏餅を作りました。近畿以西では自生しない柏の代用としてサルトリイバラを使います。
サルトリイバラの根には薬効成分があるそうですよ。
今年も、菖蒲葺で邪気除けした竹屋の離れで”どうして柏餅を食べるのか”など、昔からの風習をお勉強する会を催します。
詳細はコチラから☆
東城本店 女将
日々研究☆
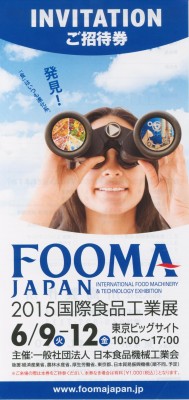 本日社長は終日出張。大規模な食品工業の展示会に勉強に出かけました。
本日社長は終日出張。大規模な食品工業の展示会に勉強に出かけました。
饅頭の作り方は創業当時から変わりませんが、家訓にもある通り、時代に順応して更に改良できるよう、日々研究しております。
東城本店 谷
三杯の茶
 竹屋饅頭と一緒にお茶をお出しする時心がけている事があります。相手の気持ちになること。
竹屋饅頭と一緒にお茶をお出しする時心がけている事があります。相手の気持ちになること。
豊臣秀吉が長浜城主だったころ、鷹狩りの帰りに立ち寄った寺で、茶を所望しました。そのとき寺の小坊主だった佐吉(のちの石田三成)が茶を入れたのですが、それを最初は飲みやすくぬるめに、次は少し熱め、最後は熱々の茶を出したそうです。喉の渇きに応じて茶の熱さを変えて出すという機転に感心した秀吉に才能を見出され、三成は取り立てられたそうです。相手の喜ぶようにして差し上げる事、難しいですね。
東城本店 女将
ムシトリナデシコ
綺麗なピンクの花ですが、ムシトリナデシコという名前だそうです。満開になると葉の下の茶色い部分からネバネバした液を出して虫を捕まえるとか!花言葉は「しつこさ」「罠」(苦笑)
東城本店 女将
« Older Entries Newer Entries »